毎年1月に行われる共通テスト、多くの医学部受験生にとっては重要な試験です。ここから次の2次試験まで1ヶ月程度あります。筆者は現役時と浪人時で共通テストの得点率は大きく変わりませんでした。しかし浪人時の2次学力の伸びを考慮しても合格した要因はこの1ヶ月の過ごし方だったと考えています。現役時は漠然と勉強を続けていましたが浪人時は十分な対策を行った上で余裕をもって受験に臨むことができ合格することができました。ここでは筆者のどのように1ヶ月を過ごしたらよいかお伝えしたいと思います。①〜④は行うべき順番です。
①共通テストの自己採点:各予備校からの試験の総評を参考に自分がどの程度の成績であったか評価する。
②受験大学の選定:滑り止めや試験慣れの為に複数の大学を受験するか、2次試験の配点や難易度などからどの大学が候補となるか、願書取り寄せをしておく。
③受験校決定、受験の為の準備:ホテル/交通の確保。願書提出。
④試験対策:赤本およびこれまでの学習の復習、どの分野を行うか
①共通テストの自己採点:各予備校から速報として解答が出されます。なかなか思う通りの点数が取れず、自己採点は精神的に辛いかもしれませんが早めに行うべきです。その後点数に一喜一憂するのではなく客観的な分析を始めます。ポイントは「全体の医学部受験生と比較して自分は優位な成績なのか、それとも遅れをとっているのか」、「過去の受験生と比較してその点数で合格する可能性はどの程度なのか」 この2点です。 予備校サイトでは各大学における共通テストのボーダーが出されます。自分の得点率がそれより良いか、悪いか確認し多くの受験生における自分の立ち位置を確認します。「ボーダーを少し上回っているからある程度2次で失敗がなければ合格の可能性が高い」「ボーダーを大きく下回っているからこの大学は難しいだろう」この様に簡単に分析していきます。
次に過去の受験生との比較を行います。受験サイトでは過去の受験生の合格最低点・合格最高点が掲載されています。(医学部 共通テスト 合格最低点などで検索してみてください。)これを自分の得点率と比較します。過去の共通テストの難易度が違うため一概には言えませんが大体この点数で合格することができるかどうかの判定にはなります。こうして過去/現在の受験生と自分を比較することで合格の見込みはあるのか判断していきます。自分を客観的に判断することは難しいですが少しでも合格率を上げるためにもやるべきだと思います。
②受験大学の選定:上記を終えた後に受験校を選定していきます。ある程度全体の受験生における自分の立ち位置がわかった上で具体的な選定に入っていきます。
まずは何校受けるのか? 私立大学を含めると5ー6校受験することも可能です。しかし受験校を増やすと移動やストレスもあり体調を崩す、勉強のペースが狂うなど支障がでてきます。筆者は場馴れや滑り止めの用途であれば1−2校の受験が妥当だと思います。
そして一番重要なのは第一希望校の決定です。これは現実的に合格できる可能性のある大学を考えていくことになると思います。ここからは2次試験の配点と自分の実力を考えて2ー3個に絞っていきます。2次試験は各大学によって配点が大きく異なり、それぞれの問題の難易度・合格基準も異なってきます。「数学が得意である程度差をつけられる自信がある」のであれば数学の配点が大きく難易度も高めの大学を考えていくのも一手だと思います。また、「共通テストである程度合格ボーダーより上の得点率だった」のであれば2次試験は配点が低く、比較的差がつきにくい大学を受験すると合格率は高くなります。 受験サイトではこの様な2次試験の特徴を解説したサイトもあるので参考にしてよいと思います。また実際に赤本で内容を確認しどれぐらいの難易度かチェックするのもおすすめです。(なかなか共通テスト後に選定していくのは大変なので時間があるのならば早めに確認することをおすすめします。)
そして2−3個の候補が決まればすぐに願書を取り寄せます。 なかなか勉強に忙しく願書取り寄せは後回しになりやすいです。早めに取り寄せておくことで精神的な余裕が生まれるのでおすすめします。(後で受験校が決定すれば使わないものは破棄すればOK)
ここまでを1月下旬には終わらせておくべきだと思います。
*国公立の出願期間は1月下旬〜2月上旬となるため
③受験校決定、受験の為の準備
この時点で2〜3校の候補に絞られています。後は自分の意思になってきます。2〜3校の中には「他の候補大学より合格確率が下がるけど行きたい大学」「合格しやすいけどあまり行きたくない大学」などでてきます。重要なのは最終決定はモチベーションに関わってくるので自分で決定すべきということです。「自分は本番に弱いタイプだから少し失敗しても合格できる大学を受けよう」「この大学に行きたいから少し厳しいけど後1ヶ月なんとかすれば合格できる」どれも正解だと思います。
あえてもう一度お伝えしますがここで重要なのは自分で決めることです。
筆者はある程度受験生から相談を受けることが多かったのですが受験後に「あのとき先生に言われたから受験したけどこうしていれば…」と悔やむ受験生も見てきました。 どうしても受験の制度上、満足の行く結果が得られない場合もありますが自分で決めずに失敗することは本当にもったいないと思います。受験の際に親族や先生からアドバイスをもらうことはよいと思いますが最終的に受験するのは自分です。流されずに自分で決めるようにしていくことで勉強のモチベーションも上がるのでおすすめします。
受験校が決まればすぐに受験地の情報とホテル予約を行います。近いホテルはどんどん埋まっていくので2月初旬にはおさえておくことをおすすめします。
④試験対策:赤本およびこれまでの学習の復習、どの分野を行うか
最後に受験対策となります。赤本での出題傾向を確認しどの分野を重点的に学習するか考えていきます。現実的に1ヶ月(複数受験や受験準備など考えると3週間前後)で全ての復習は難しいです。「微積の問題が必ず出題されるから対策しておく」「英作文が難しいので毎日継続していく」ここからは要点を絞って対策し本番に備えることで少しでも合格率を高めていきます。また、赤本で時間配分を考えていくこともおすすめです。
たった1ヶ月ですがしっかり対策をとることで逆転合格も可能だと思います。精神的に一番辛い時期ですが乗り越えて良い結果が得られることを願っています。

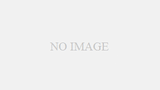
コメント