過去問対策の重要性
当たり前の事ですが受験において最終目標は「合格」です。合格するために勉強時間・勉強方法を意識して学習していく必要があります。
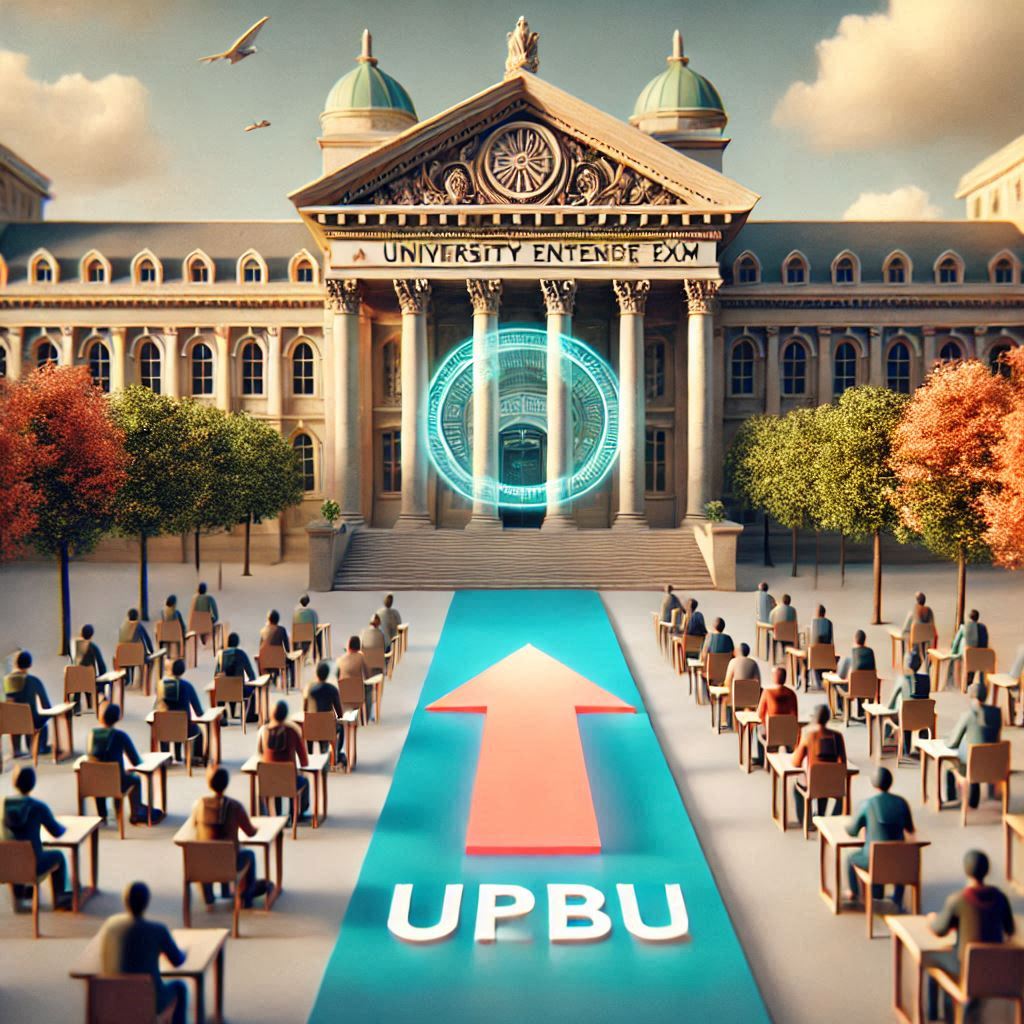
医学部受験において2次試験対策は最重要といえます。具体的には赤本研究です。私は現役時代はあまりしっかりしていなかった(する余裕がなかった)のですが受験を振り返ると非常に重要だと思います。
この理由としては2点挙げられます。
1「合格達成に必要な能力はどの程度なのか」
2「どの単元を重点的に学習すればよいのか」
上記を知ることが出来、学習効率が良くなります。それぞれ詳しく説明していきましょう。
1「合格達成に必要な能力はどの程度なのか」
一度書店などで赤本を確認して欲しいのですが各大学によって出題問題の難易度は大きく異なります。例えば
A大学は大問5題を出題、いずれも基礎的な問題ー合格ラインは8割以上
B大学は大問3題出題、いずれも難問ー合格ラインは4割程度
この様な傾向があるとします。A大学を受験する場合は1問のミスが致命的となります。勉強方法としてはより基本知識の漏れがないように基礎的な問題を素早く、正確に解いていく訓練が重要となってきます。実際に自治医科大学の入試問題は共通テストの様な問題が多く時間内に解ききることが難しく設定されています。B大学の様に難問が多い場合は完答が難しく設定されています。途中点等、考え方で部分点を稼いでいくような戦略となるためより解法へのアプローチを筋道立てていく訓練が重要です。
赤本研究(過去問対策)をすることで重点的に勉強すべき内容がわかってきます。先に述べたような自治医科大学志望の場合:共通試験の様な基礎問題を素早く解けるよう計算・暗算を重点的に学習していく。東大/京大、京都府立医科大学など志望の場合:より解法や考え方を重視した勉強にシフト、「大学への数学」や「名門の森」/「難問題の系統とその解き方」などの問題集までこなしていく、対策を変えることで合格率も変わっていきます。
筆者は最終的な到達点が変わるのであればなるべく早めに対策していくことが重要だと考えます。「現在高校一年で赤本の内容が分からない」などの方はネットの情報を一読してみるのでもよいでしょう。各医学部入試問題の難易度がランク付けされていたりするので最初はその程度を把握しておくだけでも周りの受験生とは違いがでてくる筈です。志望校がある程度決まっている受験生は先に赤本を読んでおいて損はないでしょう。
2どの単元を重点的に学習すればよいのか
これも1と同様、今後の勉強方針に関わってくるので重要と言えます。当たり前ですが試験問題は出題者が考えて作成します。その為どうしても出題分野に偏りがでてきます。赤本を対策することでその傾向を掴む→一通りの学習を終えた後にどの範囲を重点的に学習すべきかがわかります。
これは医学部合格後の進級試験対策にも当てはまります。進級試験は膨大な量です。全ての試験範囲を勉強できることが理想ですが部活・やサークル・バイトをこなしながら人体の構造や疾患概念を全て把握して試験に臨むことは不可能です。そのために大学受験を突破してきた医学部生は過去問研究:特に出やすいテーマを重点的に学習し試験対策していきます。
大学受験も赤本を5ー10年確認していくと偏りがあることがわかります。「この大学は4問中1門はかならず微積の問題が出題、2−3年に1度ベクトルの問題が出題される」「化学は有機分野が必ず出題される、化合物の暗記は必須」等etc. 偏りを把握することで勉強量を減らせる可能性があります。「この分野はほとんど出ないから基礎的な知識だけおさえておこう、そのかわりこの分野は出題率が高いから深い範囲まで学習しておこう」この様に「合格するために必要な学習量」意識することで合格率は上がります。
以上、2点のためにも赤本での対策は必要と考えます。もし書店に立ち寄る機会があれば一度目を通してみて下さい。

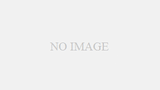
コメント